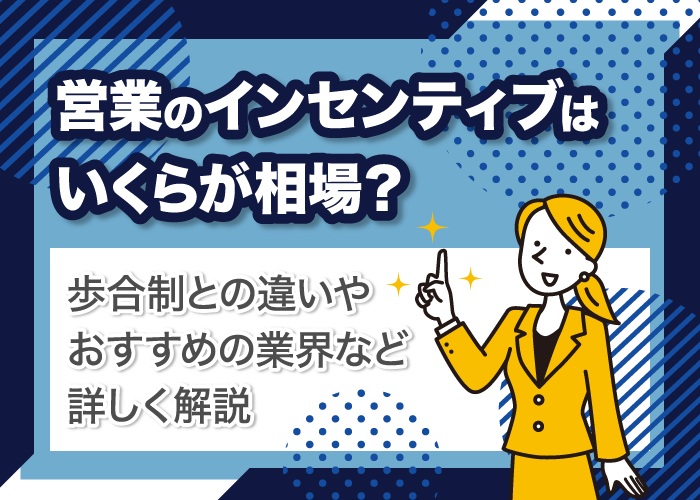記事に登場するキャラクター

Aさん
営業職への就職を考えている就活生。インセンティブの獲得に魅力を感じており、インセンティブの相場やおすすめの業界などが気になっている。

神奈川トヨタ自動車 リクルート室 室長
神奈川トヨタ自動車の採用担当。 数多くの面接を担当するほか、会社説明会・入社後研修など様々な採用シーンで活躍。 就活生の気持ちに寄り添いながらも、採用者目線でアドバイスします。
 Aさん
Aさん高い収入が見込める企業に入社したいので、インセンティブ制度がある企業の営業職を目指したいと思っています。



目標が明確なのは良いことですね。
インセンティブがモチベーションになれば、組織内での自身の成長も見込めるはずです。



ただ、インセンティブについてわからないことが多くあり、困っています。
例えば、インセンティブは「売り上げの何%支給される」のように相場があるのでしょうか?



その通りです。
インセンティブは企業によって異なりますが、おおよその相場が存在します。
インセンティブを多く獲得したいのであれば、どのような業界が良いかも知っておくと良いでしょう。



インセンティブについて、もっと詳しく聞かせてください。



わかりました。
それでは、まずインセンティブと歩合制の違いから始め、インセンティブの相場、おすすめの業界やインセンティブの種類など、詳しく解説していきます。
インセンティブ制度と歩合制、完全歩合制の違い
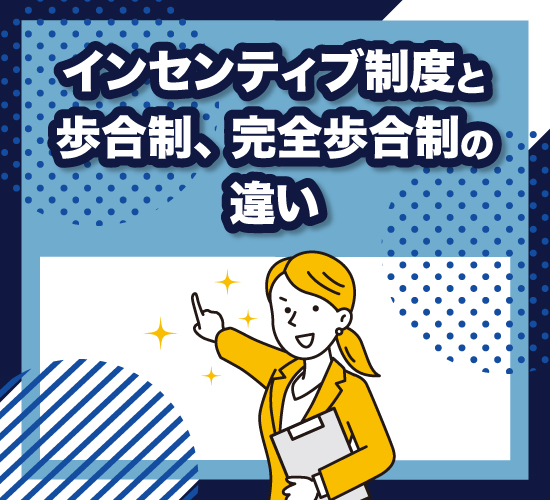
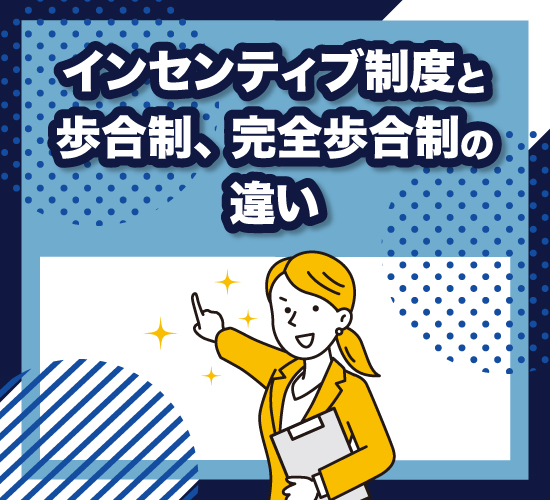
営業職を目指す方がまず押さえたいのが、インセンティブ制度と歩合制、完全歩合制の違いです。
ここで、それぞれの違いについて見ていきましょう。
インセンティブ制度とは
インセンティブ制度とは、企業が社員に対して、仕事の成果に応じた報酬を支給する制度のことです。
支給される報酬は、インセンティブや営業インセンティブなどと呼ばれます。
具体的な報酬としては、達成した目標に応じた報奨金、自社の株式や金券、賞品などが一般的ですが、表彰や人事評価といった金銭以外のインセンティブが与えられることもあります。
営業職はインセンティブが金銭で支給されることが珍しくなく、自身の頑張り次第で収入を大きく増やせることから、人気の職種の一つです。
なお、「インセンティブ(incentive)」は、「動機」や「刺激」などを意味する言葉です。
まさに、営業職が業務に積極的に取り組む動機や、営業職同士が切磋琢磨する刺激になっているといえるでしょう。
インセンティブ制度は、企業が売り上げを伸ばして社員は収入を増やせるという、良好な関係を築くために導入されています。
歩合制とは
歩合制とは、成果(出来高)に応じて追加の報酬が支払われる制度のことです。
出来高制や出来高払制、コミッション制度とも呼ばれ、委任手数料や周旋料として支払われる報酬は、歩合給と呼ばれます。
インセンティブ制度と似ていますが、インセンティブは「目標を達成したら○円」のように基本給に追加報酬として設定されるのに対し、歩合制は、契約件数などの成果や売上に応じて支払われる給与に違いがある形態を指します。
歩合制を導入している企業でも、最近では「固定給+歩合給」の構成が基本です。
「固定給+歩合給」の場合、労基法第27条により成果(出来高)が少ない場合でも、通常の給与の6割ほどは保障されていますが、その割合は企業により違いがあります。
なお、企業によっては、インセンティブ制度と歩合制を同じ意味で使っていることもあるため、注意が必要です。
参考:厚生労働省「賃金に関する労働基準関係法令等について(厚生労働省資料)」
完全歩合制とは
完全歩合制は、完全出来高制やフルコミッション制とも呼ばれており、成果(出来高)に応じて追加の報酬が支払われる制度の一つです。
ただし、歩合給と違い、完全歩合制には固定給そのものがありません。
歩合給のみで給与が決まるため、成果(出来高)がない月には、まったく給与が支払われないことがあります。
その分、契約1件あたりの報酬が多く設定されていることがありますが、収入の安定性が大きく欠ける点に注意が必要でしょう。
なお、完全歩合制は、労働基準法で保護されていることから、雇用している社員には採用されていません。
基本的には、個人事業主へ業務委託するようなケースでのみ採用されている制度です。
営業のインセンティブの相場とは
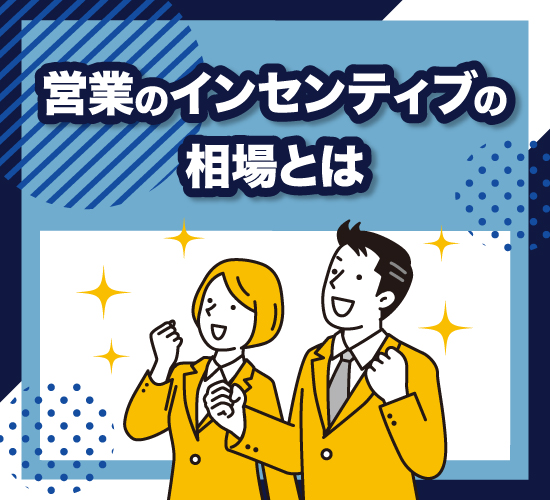
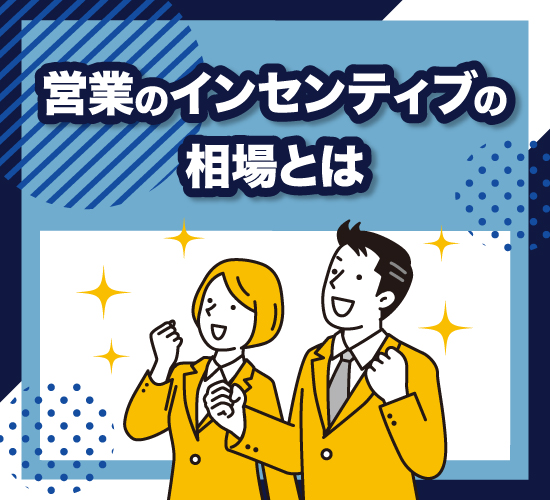
上述の通り、インセンティブは、目標の達成に応じて報酬が支給されるのが一般的です。
ここでは、特に報奨金のインセンティブの相場について詳しく見ていきましょう。
・目標超過分の売り上げの10~20%が相場
・業界によってインセンティブの割合や内容は異なる
目標超過分の売り上げの10~20%が相場
営業職のインセンティブの相場は、目標を超過した分の売り上げの10~20%といわれています。
売り上げに目標金額が設定されている場合、目標金額までは固定給の範囲でインセンティブは付きませんが、達成していれば超過分の売り上げに対してインセンティブが付きます。
例えば、目標金額が20万円で、目標を上回る60万円を売り上げたとしましょう。
この場合は、目標金額より超過している分の40万円に対し、インセンティブが付きます。
インセンティブが10%の場合、40万円×10%で4万円、インセンティブが20%であれば40万円×20%で8万円が支給される計算です。
自身の頑張り次第で、月に何十万円という金額のインセンティブをもらえる可能性があり、その点で営業職は、収入を重視したい方に適しているといえます。
業界によってインセンティブの割合や内容は異なる
インセンティブの割合は、一般的に10~20%が相場といわれていますが、業界や企業によって違いがあります。
例えば保険業界では、契約件数ではなく、契約した案件の「年間保険料の20~30%」が相場といわれており、不動産業界では、契約した案件の「仲介手数料の5~15%」が相場といわれています。
企業・業態によってはインセンティブの名称が使われていなかったり、インセンティブの条件が異なったりするため、就職先を選ぶ際には注意が必要です。
なお、自動車業界の中でも、ディーラーの場合は、車の販売台数や保険・サービスなどの契約件数によって、インセンティブが支給されることが多いです。
他にも、契約件数や売り上げ以外に、ポイント制になっていて、期間中に獲得したポイント数によって支給される報酬の内容が変わったり、支社や店舗などチームでの目標を達成したらメンバー全員に報酬が支給されたりするなど、さまざまなケースがあります。
営業職でインセンティブを獲得したい方におすすめの業界





営業職のインセンティブの相場は、売り上げの10~20%といわれているんですね。



はい。業界はもちろん、企業や業態などによっては、相場より低いことも高いこともあるため、あくまでも目安として捉えてみてください。



収入を増やしたいのなら、相場よりインセンティブの割合が高い企業を選んだ方が良いでしょうか?



一概にそうとはいえません。
インセンティブの割合が高くても、1件あたりの売り上げ金額が低い場合もあるので、その場合は思ったよりも収入が増えないことがあり得ます。



割合だけでなく、1件あたりの売り上げがどの程度見込めるかも大事なんですね。



では次に、インセンティブの獲得を目指している方におすすめの業界について見ていきましょう。
自動車業界
自動車業界は、インセンティブを稼ぎたい方におすすめの業界の一つです。
特に自動車販売会社はインセンティブ制度を導入している企業も多く、インセンティブを獲得しやすい傾向があるためです。
自動車という商材自体の価格は高いものの、必需品と考えている人は多く、国内のどの地域でも大きな需要があります。
また、分割払いやローンなどの支払い方法も充実しているため、実際には、自動車は幅広い世代の方に必要とされる商品といえるでしょう。
新規顧客や既存顧客へ積極的に来店を促す必要はあるものの、基本的に店舗に訪れる方は「車が欲しい」と考えているため、成約につなげやすいという特徴があります。
また、一度自動車を購入したお客様とは、車検やメンテナンスのご案内などで、長く付き合うことになります。
そのため、一度きりでなく、長期的にお客様とお付き合いしたいと考えている方に向いています。



トヨタモビリティ神奈川では、営業職を募集しています。
トヨタモビリティ神奈川は、神奈川県を拠点とする、トヨタの新車や中古車を扱うディーラーです。
自動車業界に就職を考えている方は、ぜひ一度、会社説明会に参加してみください。
会社説明会|採用サイト|神奈川トヨタ自動車株式会社
IT業界
IT業界も、インセンティブ獲得を目指す方におすすめできる業界といえます。
IT業界は、情報技術を活用してさまざまなサービスや商品を開発し提供する業界で、デジタル社会の昨今、成長分野として伸び代があるためです。
商品には、パソコンやスマートフォン、ネットワーク機器などのハードウェアを始め、さまざまなものがあります。
ITソリューションを図るため、自社で開発したソフトウェアやアプリケーションを売り込んだり、システムやクラウドサービスの導入を企業に提案したりすることもあるでしょう。
インセンティブ制度が導入されているIT企業にも差はありますが、特に外資系IT企業はインセンティブが高い傾向があります。
外資系IT企業は、インセンティブを含めると年収1000万円を目指せることもあります。
しかし、日系IT企業は、インセンティブを含めても、50代の年収が1000万円に届かないこともあり、企業によって様々です。
もちろん、インセンティブの獲得しやすさは、企業の規模や扱う商材などによっても変わってくるでしょう。
そのため、外資系か日系かというだけでなく、どのような企業で、どのような商材を扱っているかというところも確認する必要があります。
参考:経済産業省「我が国におけるIT人材の動向」
保険業界・不動産業界
保険業界や不動産業界も、インセンティブ獲得を狙う方にはおすすめの業界といえるでしょう。
まず、保険業界は「年間保険料の20~30%」がインセンティブの相場といわれており、一般的な営業職よりもインセンティブが高く設定されていることが多く、自身次第では収入を増やせる可能性があります。
また、不動産業界は、「仲介手数料の5~15%」が相場といわれる業界です。
インセンティブの割合が少ないことはありますが、不動産は取り扱う商材の金額が大きく、自然とインセンティブの金額も高まりやすいという特徴があります。
ただし、どちらの業界も、インセンティブ以外にも考慮するべきことが多いでしょう。
超高齢社会を迎えた現在、保険業界は加入者が減っていることから、不安定な業界ともいわれています。
また、不動産業界は、厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、離職率は16.3%です。
不動産業,物品賃貸業の合算であり、営業職のみの離職率ではないものの、産業別に見ると4位の離職率の高さがあるため、その点に注意が必要でしょう。
参考:厚生労働省「-令和5年雇用動向調査結果の概況-」
インセンティブの種類
インセンティブの獲得を目指したい就活生が覚えておきたいのが、インセンティブにはさまざまな種類があることです。
中には、収入に直接関わらないインセンティブもあります。
ここでは、主なインセンティブの種類について、6つご紹介します。
物質的インセンティブ
物質的インセンティブとは、金銭やモノで支払われるインセンティブのことです。
営業職のインセンティブは、固定給にプラスして報奨として金銭が支払われるケースが一般的です。
ただし、企業によっては、金銭ではなく下記のような形で支払われることがあります。
|
物質的インセンティブの中でも金銭的な報酬を求めている方は、どのようなインセンティブが用意されているか確認する必要があります。
評価的インセンティブ
評価的インセンティブとは、成果を評価するという形で与えるインセンティブのことです。
昇進や昇格など、物質的に与えられないインセンティブは、評価的インセンティブに含まれます。
昇給を伴う昇進や昇格であれば、固定給が上がります。
そのため、収入の増加を目指している方にとっては、評価的インセンティブも重要なものといえるでしょう。
また、評価の仕方はさまざまで、優れた成果を上げた社員を褒める、発表する、表彰するといったものも、評価的インセンティブに数えられます。
事務職や技術職のように、成果を具体的な数値で表しづらい職種では、その努力やチームワークなどを評価する目的で、評価的インセンティブが取り入れられていることがあります。
人的インセンティブ
人的インセンティブとは、社内の人間関係によって作り出すインセンティブのことです。
例えば、社員教育の実施や、チーム間のコミュニケーションを促進する仕組み作りなどが、人的インセンティブに該当します。
社員教育によって知識やスキルを高め、ハラスメント対策研修や自己啓発などに取り組むことで、所属する社員の良好な人間関係構築を目指します。
人間関係で仕事を辞めることは珍しくなく、尊敬できる上司や、知識やスキルがあって親しみやすい先輩社員などがいれば、モチベーションや帰属意識が高まり、離職率を低減することが可能です。
また、チーム間のコミュニケーションを促進する仕組みがあることで、よりチームと一緒に働いているというやりがいを引き出すこともできます。
上司や先輩の働きを積極的に学べるジョブシャドウイングや、組織のリーダーを目指す方向けにリーダーシッププログラムなどを導入している企業もあります。
理念的インセンティブ
理念的インセンティブとは、企業の理念によって生み出すインセンティブのことです。
例えば、経営陣が定期的に事業の意義を発信したり、成果を報告したりということが挙げられます。
こうした活動により、社員が「自身の業務が社会の役に立っている」、「この仕事は社会に必要なこと」というように認識してくれる効果が見込めます。
企業は、事業を通して実現したいこと(ビジョン)や、社会で担っていくべきと考える役割(ミッション)、企業が大切にしている価値観(バリュー)など、さまざまな企業理念を持っています。
就活生もまた、これらの企業理念に共感して、入社することになるはずです。
直接的な収入アップは見込めないものの、物質的インセンティブや評価的インセンティブを獲得するためのモチベーションや、自己肯定感を高める効果が見込めることから、採用している企業もあります。
福利厚生的インセンティブ
福利厚生的インセンティブとは、報酬として福利厚生制度の利用権を与えるインセンティブのことです。
例えば、下記のような福利厚生制度を利用できることがあります。
|
休暇には、リフレッシュ休暇やアニバーサリー休暇、誕生日休暇などを選べることがあります。
健康増進手当は、ヨガやフィットネス、ジムなどの利用費を、福利厚生費として企業が負担してくれるものです。
食事支援では昼食代のサポートが受けられ、従業員持ち株制度では、自社の株を購入する機会がもらえることがあります。
自己実現インセンティブ
自己実現インセンティブとは、社員の自己実現を企業がサポートするインセンティブのことです。
例えば、社員が希望している業務に挑戦しやすい、希望している部署への異動が認められやすいなどが挙げられます。
新入社員であれば、自信が付いてチャレンジしたいと思える仕事があっても、なかなか任せてもらえないということは多いでしょう。
また、入社後に希望部署に配属されず、しばらくそのまま働いていたものの、やはり希望部署へ異動をしたいと思うこともあるかもしれません。
企業にとっても、そのような状況は社員のやる気を損なわせたり、社員が辞職してしまったりというリスクがあり、マイナスになることがあります。
そのため、希望している業務に挑戦しやすい、異動の希望が通りやすいなど、制度を整えている企業もあるのです。
さらに、セミナーや研修制度などで、知識やスキルを獲得できる機会を設けている企業も、自己実現インセンティブを整えている企業といえるでしょう。
インセンティブがある企業に就職するメリット
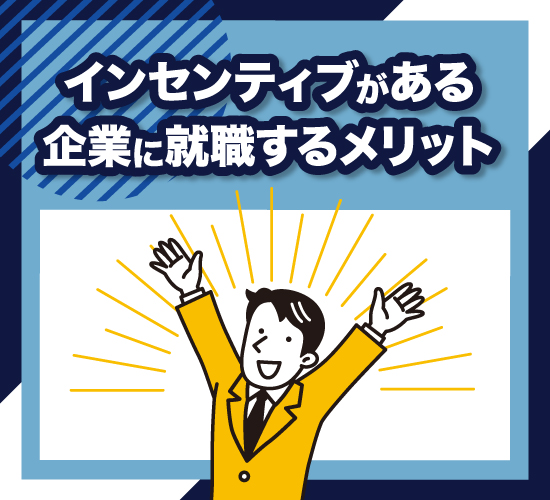
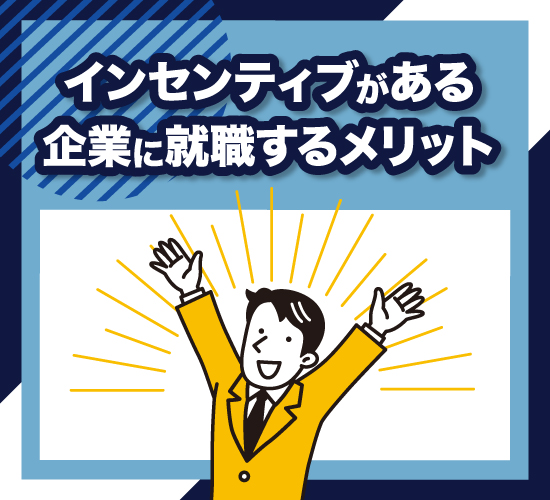
上述のように、インセンティブにはさまざまな種類があります。
それぞれメリットはありますが、ここでは、特に金銭で報酬が支払われる物質的インセンティブのメリットについて見ていきましょう。
・モチベーションを高く保てる
・自身次第で収入増加が見込める
・目標がシンプルになる
・営業スキルを高めやすい
・評価を実感しやすい
・実績は転職時のアピールポイントに
モチベーションを高く保てる
インセンティブが受け取れる企業に就職することで、モチベーションを高く保ちやすいというメリットがあります。
目標を達成することが、金銭的な報酬に直接つながっているためです。
営業職に目標はつきものですが、ただ目標が設けられているだけでは、目標を達成することにやりがいは感じにくいかもしれません。
しかし、目標を達成することが収入増加につながるのであれば、やりがいになります。
高いモチベーションを保って業務に当たり、パフォーマンスを発揮できるはずです。
自身次第で収入増加が見込める
自身の努力次第で、収入増加が見込めることもメリットでしょう。
就職する業界や企業などによりますが、インセンティブを含めた年収が、同世代の平均年収を超えることがあり得るためです。
収入が増加すれば、今の暮らしを充実させたり、結婚や子供といった将来のことを考えたり、老後に備えたりと、人生の選択肢が広がります。
また、実力主義で学歴や資格は重視されにくいことも、人によってはメリットと感じられるはずです。
コミュニケーション能力や営業力など、実力さえあれば、どなたでも収入アップを目指せます。
目標がシンプルになる
自身の目標を明確にできることも、インセンティブ制度がある企業に就職するメリットです。
例えば、「課された目標を達成しよう」というのは、シンプルでわかりやすい指針です。
インセンティブ制度がないことから、何が評価されるのか分からなかったり、昇給や昇進、賞与などにつながるポイントが判断できなかったりすると、目標を見失ってしまう場合があるかもしれません。
インセンティブ制度があることで、販売件数、契約件数、売り上げなど、評価されるものが明確になります。
自身が注力するべきポイントがわかり、企業にとっても自身にとっても、正しい方向性で仕事に取り組めるようになるはずです。
営業スキルを高めやすい
インセンティブ制度がある企業では、自身の営業スキルを高めやすいというメリットもあります。
特に、物質的インセンティブを目当てにしている方は意欲も高く、「目標を達成するにはどうすれば良いか?」と、自然に試行錯誤や努力ができるためです。
営業スキルを高めるために、先輩や上司の営業手法を真似したり、まだ他の人がやっていない手法を実行してみたりと、さまざまな行動を起こせます。
また、起こした行動は、目標が達成できなかったときも無駄にはなりません。
「次はどうすれば目標を達成できるか?」と、失敗の原因を分析すれば、より高い営業スキルが身に付くはずです。
評価を実感しやすい
評価を実感できることも、インセンティブ制度がある企業に就職するメリットでしょう。
自身の努力が評価されれば、報酬というわかりやすい形で与えられるためです。
報奨金が支給されない場合、目標を達成しても、給与はそれほど変わりません。
賞与が増えるなどがあったとしても、自身の努力がどのように評価され反映されているのか評価基準がわかりづらいこともあるでしょう。
しかし、インセンティブ制度があれば、目標に対して評価されることが明確なため、評価を実感しやすいでしょう。
物質的インセンティブ以外の評価的インセンティブで評価される場合でも、自身が企業の役に立っているという実感を得たり、企業を居場所として大切に思えたりと、メリットが多いはずです。
実績は転職時のアピールポイントに
インセンティブ制度がある企業では、転職時にアピールポイントになることがあります。
何件販売できたのか、売り上げにどの程度貢献できたのかなど、具体的な数字で表せれば、自身の営業スキルを転職活動時の面接や履歴書などでアピールすることができます。
また、自身がインセンティブを獲得するためにどのような努力を重ねたのか、失敗をどのように挽回したのかなど、具体的なエピソードも添えることができれば、より説得力のあるアピールポイントになります。
転職を視野に入れて働きたいという方にとっても、メリットがあるといえるでしょう。
インセンティブがある企業に就職するときの注意点
さまざまなメリットがあるインセンティブ制度ですが、注意したいこともいくつかあります。
ここでは、インセンティブ制度がある企業に就職する際に考慮したい、注意点について、5つ見ていきましょう。
・目標がプレッシャーになることがある
・収入が月ごとに変わる
・チームワークを発揮しづらい企業もある
・評価されない業務に面倒さを感じる人も
・固定給や賞与が低いことがある
目標がプレッシャーになることがある
人によっては、インセンティブ制度がモチベーションにつながらずプレッシャーに感じられることがあります。
例えば、毎月目標が課されている場合、日々数字を追わなければならない状況に疲れてしまったり、人と競争することや比較されることに精神的負担を感じてしまったりするかもしれません。
インセンティブ制度を利用して、収入増加を目指したいという方は、自身の性格が営業職に向いているかどうかも考える必要があるはずです。
収入が月ごとに変わる
収入が月ごとに変わることも、人によってはデメリットと感じられるでしょう。
インセンティブ制度を導入している企業では、課された目標を達成できるかどうかが、収入に影響するためです。
もちろん、インセンティブで収入が増やせるのは、チャンスでありメリットです。
しかし、思ったよりも実力が発揮できない月があったりすると、その月の収入は落ちてしまいます。
自身次第で収入が不安定になってしまうことに、不安を感じる方もいるかもしれません。
チームワークを発揮しづらい企業もある
インセンティブ制度があることで、チームワークが発揮しづらい企業もあります。
店舗や支社での目標を優先してチームを組ませる企業もあれば、個人の切磋琢磨を促すために個人に目標を設定する企業もあり、目標設定は企業によって様々です。
チーム目標を重要視している企業では、営業スキルが高い方から営業手法を学んだり、アドバイスを受けたりする機会が多く、営業職同士でも高め合ったり協力したりできます。
しかし、個人目標を重要視している企業では、自身での成長を重視することから、協力がしづらくチームワークを発揮しづらい企業もあるでしょう。



トヨタモビリティ神奈川では、店舗という一つのチームで目標を追いかける体制を構築しています。
営業職で活躍したいものの、社内で競争をするよりも協力し合いたいという方に向いている職場です。
自動車業界の営業職に興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
営業職募集要項|採用サイト|神奈川トヨタ自動車株式会社
評価されない業務に面倒さを感じる人も
インセンティブ制度が採用された企業では、評価されない業務に対して後ろ向きになってしまうことがあり得ます。
例えば、個人の携帯ではなく、オフィスにかかってきた電話の応対や来客応対、社員同士のコミュニケーション、事務作業などです。
インセンティブにつながるのであれば、パソコンで資料を作成したり、データ入力したりという事務作業も前向きになれるでしょう。
しかし、「この業務はインセンティブ獲得につながらない」と損得勘定が働くと、自身の営業に関わる業務以外は面倒さを感じてしまうという人もいます。
固定給や賞与が低いことがある
インセンティブ制度を採用している企業の中には、固定給や賞与が低く設定されていることがあります。
インセンティブ制度によって営業職が収入をアップさせやすいと、その分、他の社員との差ができやすくなってしまうためです。
特に、歩合制を採用している企業であれば、その傾向は顕著でしょう。
歩合給を稼げなければ、収入が抑え気味になってしまうリスクがあります。
まとめ
この記事では、インセンティブと歩合制がどのように違うか、またインセンティブの相場がいくらか、おすすめの業界やインセンティブの種類など、詳しくご紹介しました。
営業職におけるインセンティブの相場は、目標を超過した売り上げの10~20%といわれています。
インセンティブによって収入を増やすことができれば、今の生活が充実につながり、将来の選択肢も広がります。
インセンティブ制度を導入しているかどうかは、入社前に確認することができますが、企業によってはインセンティブの内容や条件などは入社後に明らかにされることもあります。
気になる場合は、会社説明会などで質問してみたり、業界の傾向などを調べてみたりすると良いでしょう。
また、インセンティブの内容以外にも、取り扱う商品の販売しやすさや業界研究など、さまざまな部分を確認しながら、営業職を目指してみてください。