2025.05.08
罰則もある?社用車のアルコールチェック義務化について解説!
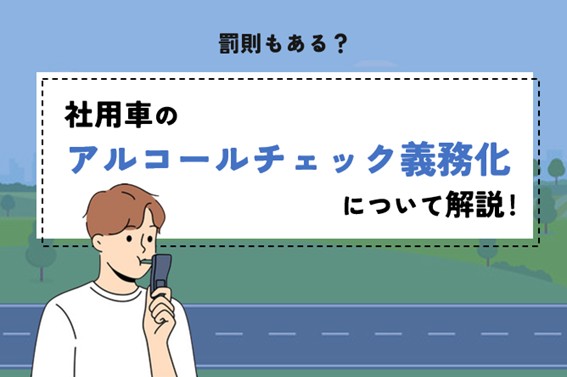
令和4年(2022年)、社用車のアルコールチェックが義務化されましたが、チェック義務の対象者 や運用方法について気になる方も多いでしょう。
今回は社用車のアルコールチェック義務化について詳しく解説します。
アルコールチェックの義務化とは
令和4年(2022年)年4月から社用車のアルコールチェックが義務化されました。
社用車として使用されている車における、飲酒運転防止対策を強化するためです。
改正前は旅客自動車輸送事業や貨物自動車輸送事業などを営む事業者のみに義務付けられて いたアルコールチェックが、一定台数以上の自家用車を保有する事業者にも拡大されました。
アルコールチェックが義務付けられている事業者

以下の条件 に当てはまる事業者に義務付けられています。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している
- その他の自動車を5台以上保有している
大型自動二輪車または普通自動二輪車は0.5台として計算します。
送迎車など乗車定員の多い車を保有している場合や、5台以上の社用車を保有している場合は対象となります。
法律改正の内容

アルコールチェックに関する道路交通法の改正は以下のとおり2回に分けて行われました。
令和4年(2022年)4月1日施行
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
令和5年(2023年)12月1日施行
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
令和5年(2023年)の改正により、アルコール検知器を用いてより正確に酒気帯びがないかを確認することになりました。
社用車のアルコールチェック義務化で事業者がすべきこと
事業者にはどのような義務があるのでしょうか。
具体的に解説していきます。
安全運転管理者の選任

まずアルコールチェック義務化の対象事業者は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
さらに、社用車を20台以上保有している事業者は、台数に応じて副安全運転管理者を選任する必要があります。
選定には年齢に関する要件や欠格事項があります。
過去2年以内に都道府県公安委員会から安全運転管理者の解任命令を受けた人や、交通に関する違反行為をしてから2年経過していない人を選任できません。
また、交通に関する違反を容認する人もふさわしくありません。
ドライバーになる人もそうでない人も意識を高くもち、適切に選任が行えるように努めましょう 。
また、安全運転管理者は次の業務を担います。
安全運転管理者の業務
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運転計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
- 運転者の酒気帯びの有無の確認
- 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保有
- 運転日誌の備え付けと記録
- 運転者に対する安全運転指導
引用:警視庁「安全運転管理者制度の概要」
なお、安全運転管理者の選任の際には、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出る義務があります。
アルコール検知器の導入

事業者はアルコールチェックに使用する検知器を準備しなければなりません。
アルコール検知器とは呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器です。
また、検知器が常に有効に動作するよう、正常に動作しているかどうかを都度確認し、適切に管理する義務があります。
アルコール検知器には、どこでも検知可能なハンディタイプや、据置タイプがありますが、使いやすく、管理もしやすいものを選ぶとよいでしょう。
ドライバー一人ひとりについて確認するため、複数台用意すると時間短縮になります。
記録の作成と保管

チェックの結果は記録にとり、書面もしくはデータで1年間保管しておきましょう。
記録方法にとくに決まりはなく、パソコンでも手書きでも認められ、様式も自由です。
記録は通常、社内保管となりますが、事故などの際には提出を求められる場合があります。
誰にでも見やすいように作成し、いつでもすぐに提出できるよう、適切な管理保管に努めましょう 。
記録の作成と保管にあたっては業務が増え、面倒に感じる方もおられるかもしれません。
ですがチェックの上、記録に残しておくと、万が一事故が起こってしまった場合に、酒気帯び(飲酒)運転ではなかったことの証明となります。
従業員や会社を守るための大切な資料を作っていると考え、前向きに取り組みましょう。
アルコールチェックの義務違反や飲酒運転による罰則

アルコールチェックの義務違反があった場合には、公安委員会から安全運転管理者義務違反とみなされ、是正措置命令が出される場合があります。
公安委員会の命令に従わなかった場合には、道路交通法第百十九条の二により、50万円以下の罰金が科せられます。
また、飲酒運転には厳しい行政処分と罰則があり、飲酒運転をした従業員だけでなく、車両を提供した事業主にも同等の処分が科されるため、会社としての費用や信頼の損失を防ぐためにも組織全体で飲酒運転の根絶に努めましょう。
以下はドライバーと車両提供者との罰則を示したものです。
社用車の運用にはそれほどの責任が伴うことを知り、適正に管理してください。
車両等を運転した者への罰則
- 酒酔い運転をした場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転をした場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両等を提供した者(事業主)への罰則
- (運転者が)酒酔い運転をした場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
引用:警視庁 みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
アルコールチェックで社用車を安全に運用しましょう
今回は社用車のアルコールチェック義務化について解説しました。
今回の内容を参考に安全運転を心がけながら社用車を運用してください。
神奈川トヨタ自動車では、従業員様向けの交通安全講習も行っております。
ぜひ下記ページもご覧ください。
